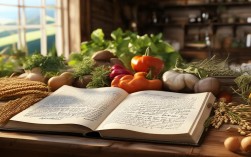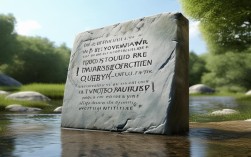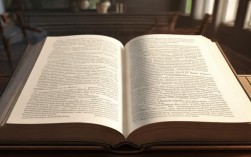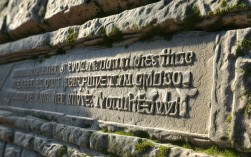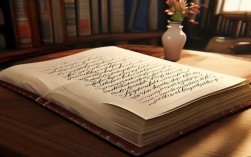心構え・精神
-
「書は心の画なり」
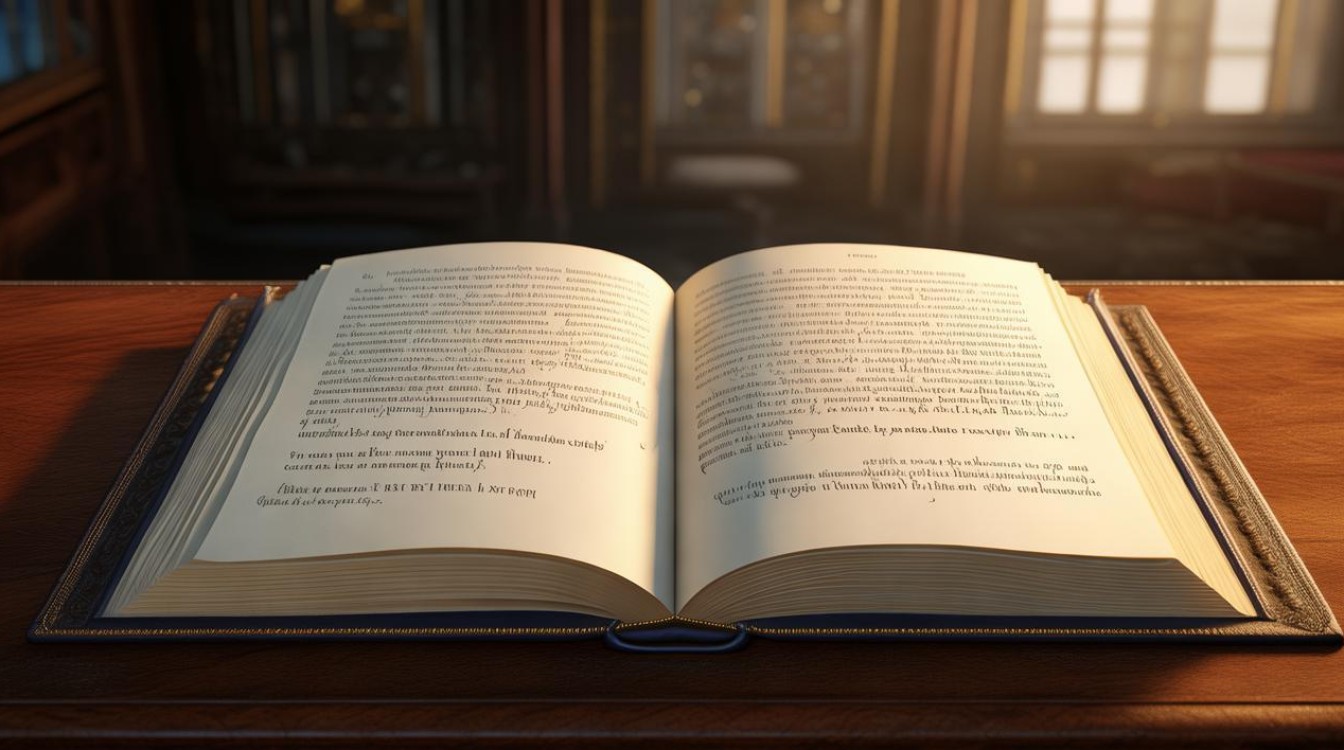
- 読み方: しょはしんのがなり
- 意味: 書は、書き手の心そのものが描かれた絵である、ということ,字は書き手の品格や精神状態がそのまま表れるという意味です。
- 関連名言: 書は心の漏れ出る所なり (しょはこころもれだるところなり)
-
「心正しくして筆正しし」
- 読み方: こころただしくしてふつただしし
- 意味: 心が正しくあれば、筆(字)も自然と正しく書ける、ということ,書の根幹は人格や精神の修養にあるという教えです。
-
「書に古を学ぶべからず、古を貫くべし」
- 読み方: しょにこをまなぶべからず、こをかんすべし
- 意味: 書の道では、ただ過去の名跡を模倣するだけではいけない,古来の法則や精神を深く理解し、それを自分のものにして、自分の表現として貫くべきだ、という意味です。
技法・腕前
-
「力を入れて書けば力あり、力を抜いて書けば力なし」
- 読み方: ちからをいれてかければちからあり、ちを抜いてかければちからなし
- 意味: 力強く書けばその力が伝わり、力を抜いて書けばその弱さが伝わる,腕前やその時の調子が、そのまま字に表れるということです。
-
「永字八法」
- 読み方: えいじはっぽう
- 意味: 「永」という一文字に、漢字の基本となる八つの筆法(点・横・竪・鉤・提・折・撇・捺)が含まれているという考え方,書の基本練習として重視されます。
-
「間(ま)」
- 意味: 書において、字と字、行と行の間隔,文字の形そのものと同等、あるいはそれ以上に重要視される概念。「余白」とも言い、美しさや躍動感を生み出す大切な要素です。
練習と修行
-
「臨池学書、池水尽く」
- 日本語読み: りんちがくしょ、ちすいつく
- 意味: 古代の書家・張芝が、毎日のように水で墨をすって練習し、使った水が池の水をすべて黒くしてしまった、という故事,書の上達には、絶え間ない努力と練習が必要であることを示す有名な言葉です。
-
「鉄砚穿つ(てつえんうがつ)」
- 読み方: てつえんうがつ
- 意味: 砚(すずり)を鉄で作り、それを使いこなすことで磨り減らしてしまうほど、ひたすらに練習を重ねること,忍耐強く、粘り強く学ぶことのたとえです。
書の境地・理想
-
「書は静なるを貴ぶ」
- 読み方: しょはしずなるをたっとぶ
- 意味: 書の最高の境地は、派手さや激しさではなく、静かで落ち着いたものにある、ということ,内面の深い平静が、静かで味わい深い書を生み出します。
-
「神・妙、能、妙、能、逸、能、佳」
- 読み方: しん、みょう、のう、びょう、のう、いつ、のう、か
- 意味: 書の品評(鑑賞)における、古来からの格付け。「神」(神の域に達している)が最高位で、「佳」(優れている)が下位,書の評価基準を示す言葉です。
中国語の名言 (中文名言)
-
字如其人 (zì rú qí rén)
- 意味: 字はその人そのものである、という意味,日本の「書は心の画なり」とほぼ同義です。
-
書為心畫 (shū wéi xīn huà)
- 意味: 書は心の描く絵である、という意味。これも「書は心の画なり」に対応する中国の言葉です。
-
意在筆先 (yì zài bǐ xiān)
- 意味: 書く前に、まずその意図や構図が心に定まっていなければならない、という意味,書き始める前の構想の大切さを説きます。
-
心正則筆正 (xīn zhé zé bǐ zhèng)
- 意味: 心が正しければ、筆も正しくなる、という意味,日本の「心正しくして筆正しし」と全く同じ思想です。
-
臨池學書,池水盡黑 (lín chí xué shū, chí shuǐ jìn hēi)
- 意味: 日本の「臨池学書、池水尽く」と同じ故事,張芝のエピソードを指す言葉です。
これらの名言は、書の技術だけでなく、書き手の精神や人生そのものへの問いかけでもあります。ご自身の書の指針として、または鑑賞の参考にしてみてはいかがでしょうか。